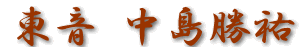[ 約2分 ]
|

在原業平(825~880)は、平城天皇の皇子阿保親王の五男で、在原の姓を下賜されました。在原の五男なので世に「在五」とも呼ばれています。六歌仙の一人ですが、紀貫之は「古今集」序で、「業平はその心余りて言葉足らず。萎める花の色無くて、匂ひ残れるが如し」と評しています。ともかく業平は、奔放で情熱的な和歌の名手で、色好みの美男とされています。
清和天皇のもとに入内する前の藤原高子(二条后)との情事で、都に居づらくなつた業平は、都に心を残しながら東国に下りますが、その話が有名になって、「東下りの忠実男」といえば、業平のことを指すようになリました。そうしたことを踏まえた歌物語が『伊勢物語』だとされています。 この歌では、東下りの道すがら、袖にかかろ紅葉葉に、ニ条后ヘの恋歌が思い出され、桜尽くしで、その恋模様を綴ります。そLて、「わが身ひとつはもとの身にして」の歌のように、我に立ち返りますが、身に沁む秋風も何のその、と暮れ泥む秋の夕日の中ヘ、また旅立って行きます。 冒頭の「きつつなれにし~」をはじめ、『伊勢物語』にも使われています業平の和歌が、歌詞の随所に散リぱめられています。 「かきつばた」を折句にした「唐衣きつつなれにしつましあれば、はるばるきぬる旅をしぞ思ふ」は、『伊勢物語』では東下りの途上、三河国八ツ橋で詠んだことになっています。「ちはやぷる神世もきかず龍田川、から紅に水くくるとは」は、『百人一首』でも有名です。そして、「世の中に絶えて桜のなかリせぱ、春の心はのどけからまし」の歌の通り、桜の花は現在でも大さなニュースになるほどで、人々の心を騒がせます。「月やあらぬ春や昔の春ならぬ、わが身ひとつはもとの身にして」も古くから名歌とされてきました。 |